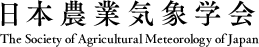日本農業気象学会長 荊木康臣
会長就任の挨拶
日本農業気象学会長 荊木康臣
2025年3月の総会での承認を経まして、2025年-2026年期の会長に就任いたしました荊木です。よろしくお願い申し上げます。本来であれば、3月にご挨拶すべきところ、ほぼ半年遅れとなりましたこと、お詫び申し上げます。この2年間、微力ではございますが、本学会の発展に向けて、皆さまのご期待に応えられるよう全力を尽くして参る所存でございます。
さて、現在、当学会の会員数は減少傾向にあります。一方、社会に目を向ければ、世界的に脱炭素社会への移行が求められる中、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や農業分野における「みどりの食料システム戦略」が提示されるなど、学術界に対する技術革新の期待が高まっています。このような状況下、気候変動の緩和策と適応策の両方を研究課題とする当学会の存在意義は極めて大きいといえます。また、スマート農業やデータ駆動型農業など、農業分野の喫緊の課題においても、気象・環境データを扱う本学会の強みが十分に発揮できるものと考えます。それにもかかわらず、会員数が減少している現状は憂慮すべき事態です。
本来、学会は研究者や技術者が集い、情報交換や成果の相互レビューを通じて学術を発展させる場であり、有益な情報や有意義な議論、最新の研究評価を得られることが参加の意義です。これらは研究者にとって研究活動の原動力となります。私自身、農業気象学会に参加することは楽しく、役に立つ情報を得る貴重な機会であり、その価値を十分に感じております。しかしながら、多くの関連する研究者・技術者の方々には、残念ながらこうした価値が十分に伝わっていないのではないかと思います。そこで、今後の活動に向けた抱負といたしまして、「参加して役立つ、参加して楽しい学会」としての魅力をさらに高め、発信することを第一に考えていきたいと思っております。
幸いなことに、平野元会長、富士原前会長の下、「学会運営業務の効率化および組織・運営体制のスリム化」のために対応すべき課題としてあげられていた、1) 学会誌の出版形態,2) 評議員会のあり方,3) 理事会のあり方,4) 支部の活動・運営,5) 学会財産の活用,6) 全国大会の開催方針,7) 学会財政の健全化,8) 研究部会の活性化,9) 永年功労会員表彰委員会のあり方、に関しては概ね検討が進み、特に学会の運営体制においては、すでに一定の効率化が図られてきました。
また、新規会員獲得に向けて、富士原前会長の指揮の下、生産現場に近い技術者や研究者に役立つ技術に関する出前講義の提供や、全国大会時に地元高校生によるポスター発表会が実施されるなど、新しい取り組みも始まっています。また英文学術誌「Journal of Agricultural Meteorology」は、編集委員会の尽力により、現在JSPSの研究成果公開促進事業の採択を受け、国際的なプレゼンスの向上が図られています。
基本的には、これらの方針を引き継ぎたいと考えておりますが、本学会が法人格を持たない任意団体であり、収益事業を行うことができないという危惧などから、これらの取り組みや今後の新しい取り組みを行う上で、制限が生まれているのも事実です。検討課題として残っている、学会財産の活用,全国大会の開催方針,支部活動や研究部会の活性化などは,この問題と直接的に関係する重要事案です。そこで本年度は、学会として実施可能な活動と実施が難しい活動とを明確化し、将来的な学会の魅力向上ならびに会員の皆様がより活動しやすい環境の整備に努めて参りたいと存じます。
私は、農業気象学会は開かれた学会であるとの印象を強く持っております。会員の皆様から頂いたご意見やご提案は、理事会等で、真摯に検討させていただきますので、積極的にお寄せください。
これからの2年間、会員の皆さまと共に農業気象学の学術の発展に寄与してまいりたいと考えております。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
2025年9月1日